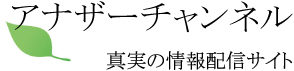・日中の活動に差が出る
・認知症になるリスク
・噛む力にも支えられている
●朝食を食べて生活習慣病の予防に
朝食を食べる習慣は生活習慣病の予防にも役立ちます。
朝食を抜くと、昼や夜に糖の吸収と血糖値の上昇が集中してしまいます。
糖を吸収する時間がずれると、エネルギーとして消費されない糖が増えてしまい、
脂肪に変わります。
糖尿病患者が朝食を食べないと、低血糖から認知症になるリスクが上がる事も
明らかになっています。
肉食を止め、動物性脂質や甘いものを摂り過ぎない事。
そして散歩やスクワットなどの有酸素運動をして、酸素を体内に取り込んで
血流を促すことも大切です。
●朝食を食べない問題
朝起きても、朝食を食べる氣にならないという人もいます。
しかし、前の食事から一定時間以上は経っているはずなので
本来はお腹が空いているものです。
食べられない原因は、食事内容やリズムに問題があると思われます。
例えば、以下のような習慣です。
・朝食を食べたがらない。
(子どもの場合はお母さんに叱られて、無理矢理朝食を食べる)
・食欲がわかなくて、昼食を食べられない時もある。
・夕方になると、とてもお腹が空く。
夕食まで我慢できなくなって、お菓子をたくさん食べてしまう。
(共働きの家庭の場合は、両親が子どもの食べ過ぎに氣づかないこともある)
・お菓子でお腹がいっぱいになり、夕食をあまり食べられない。
このような食事をしていると常に体調が悪い状態が続きます。
体力が無い、疲れやすい、落ち着きが無い、仕事中(授業中)に眠くなる、
自制心や忍耐力が欠けていて、物事が長続きしないなど
何も良いことがありません。
さらに、心理的ストレスも積み重なります。
子どもの頃から食事のリズムが狂うと、まだ自分ではどうすることも出来ないので
心身の成長ばかりか、大人になっていく将来も心配です。
なかなか食べられないのでお母さんに叱られながら、朝食を食べる。
学校でも、給食を残すと先生に注意される。
これでは学校生活も楽しくなく、辛い思いばかりです。
たとえ食欲があっても食事時間のリズムが乱れると、営養状態も悪くなります。
朝に食欲が沸かず、そのつけが夕方に来てドカ食いしてしまう。
食べるべき時に食べられず、体に悪いものを食べ過ぎたのが災いして
営養不足になっているのです。
早くに起きて、しっかり朝ご飯を食べること。
食事が美味しく食べられるようになれば、しめたものです。
食事の満足感が高くなれば、間食も徐々に減っていきます。
大人も生活習慣病になる前に、食生活の改善に努めましょう。
●朝食を食べないとキレやすくなる
欲望や衝動を抑えられず、感情が爆発したり、暴発的行動に出る。
こうした「キレる」人が増えたのは、食事の問題や生活習慣の乱れなど
様々な原因が重なっていますが、朝食を食べない事も一因です。
朝食を抜くと血糖値が低下して闘争ホルモンのアドレナリンが分泌されます。
そして交感神経が優位になり、アドレナリンを分泌させます。
一方、朝食を食べると幸せを感じたり、リラックス作用のある
セロトニンというホルモンが分泌されます。
朝ご飯を食べる人と食べない人では、朝から仕事や勉強に向かう時から
氣持ちの面でも全く違うのです。
セロトニンは睡眠ホルモンであるメラトニンの材料になりますので、
朝にセロトニンを十分に分泌すると、夜の睡眠の質を上げてくれます。
ちなみに朝食を摂らない人達には脂肪の過剰摂取、野菜不足、
間食が多いなど営養不足の傾向が非常に高いです。
ビタミン・ミネラルが慢性的に不足しているため、イライラや不安になってしまうのです。
もしこのような食生活をしていたら、まずは衝動的に食べる習慣を止めましょう。
ファーストフード、コンビニ食品、インスタントラーメン、お菓子類、
その他加工食品など食品添加物ばかりのものは、衝動性を生みます。
野菜や果物、食材から調理して食べる事が大切です。
●誤ったダイエット法
減量するためには食事量を減らすことが第一ですが、
朝食を抜いてもダイエットにはならないので注意してください。
朝食を食べないと、心身の活動を低下させてしまいます。
体はエネルギー不足と判断して、昼食や夕食で摂取したエネルギーを
脂肪として貯めようとします。
朝食で摂ったエネルギーは、日中の活動のために使われます。
でも、夕食を摂った後は寝るだけなので、食べ過ぎると
余分なエネルギーは脂肪として蓄えられます。
それは、子どもの体型にもはっきり表れます。
肥満時は、そうでない子どもと比べて、
朝食を食べていない子(または食べているが営養不足)が多いのです。
●痩せるためには朝食を食べる事
痩せる(適正体重に戻す)ために朝食を抜くのではなく、しっかり食べましょう。
健康な人の腸内には通称「ヤセ菌」がたくさんいます。
これらの菌は食物繊維をえさにして、脂肪の蓄積を抑脂肪の消費を増やします。
また、短鎖脂肪酸を作ります。
肥満の人の腸内にはヤセ菌が少ないので、脂肪細胞がどんどん肥大化されていきます。
脂っこい食べ物を食べ過ぎてしまい、どんどん太るという悪循環を繰り返すのも
腸内細菌の影響を受けています。
つまり朝食をしっかり食べ、そこへ食物繊維を入れることが大切です。
食物繊維は大きく分けると、水溶性と不溶性があります。
<水溶性食物繊維>
便を柔らかくして、お通じが良くなります。
血糖値の急上昇を抑え、消化管をゆっくり移動するので
腹持ちが良く、ダイエットに効果的。
りんごやバナナ、海藻類に豊富に含まれています。
<不溶性食物繊維>
有害物質、腸内細菌の死骸、発がん物質などを取り込んで体の外へ出します。
玄米、大豆、根菜類、野菜全般、きのこ類に豊富に含まれています。
腸内環境が改善されると代謝も良くなりますので、肥満の改善、または予防することができます。
食物繊維を摂りながら、営養バランスの取れた食事をするためにも
玄米菜食は日本人に最も適しています。
●朝食を食べないとキレやすくなる
欲望や衝動を抑えられず、感情が爆発したり、暴発的行動に出る。
こうした「キレる」人が増えたのは、食事の問題や生活習慣の乱れなど
様々な原因が重なっていますが、朝食を食べない事も一因です。
朝食を抜くと血糖値が低下して闘争ホルモンのアドレナリンが分泌されます。
そして交感神経が優位になり、アドレナリンを分泌させます。
一方、朝食を食べると幸せを感じたり、リラックス作用のある
セロトニンというホルモンが分泌されます。
朝ご飯を食べる人と食べない人では、朝から仕事や勉強に向かう時から
氣持ちの面でも全く違うのです。
セロトニンは睡眠ホルモンであるメラトニンの材料になりますので、
朝にセロトニンを十分に分泌すると、夜の睡眠の質を上げてくれます。
ちなみに朝食を摂らない人達には脂肪の過剰摂取、野菜不足、
間食が多いなど営養不足の傾向が非常に高いです。
ビタミン・ミネラルが慢性的に不足しているため、イライラや不安になってしまうのです。
もしこのような食生活をしていたら、まずは衝動的に食べる習慣を止めましょう。
ファーストフード、コンビニ食品、インスタントラーメン、お菓子類、
その他加工食品など食品添加物ばかりのものは、衝動性を生みます。
野菜や果物、食材から調理して食べる事が大切です。
●噛む力も活動を促している
朝食では営養摂取だけでなく、噛むことでもその後の一日の活動を促しています。
・脳を活性する
高齢者の脳も、噛むことで活発に働く。
・脳の運動能力が上がる。
朝食を食べること、脳や体に活動を始めるるよう働きかけています。
噛む点から見ても、朝食を食べる人と食べない人では、
日中の活動の量や質に差が出てしまいます。
よく噛んまた、で食べると満腹中枢を刺激するので、食べ過ぎを抑えられます。
朝食をよく噛んで食べれば、ダイエット効果が上がります。
朝食を食べる人と、食べない人。
食事内容が大切なのはもちろんですが、この習慣の差によって
子どものうちから学力や集中力、体力に差が出てしまいます。
「子どもの夢を応援したい」とご両親は願っていると思います。
夢を叶えていくためには、まず体力や意欲が無くてはなりません。
そういうものは予め備わっているものと思われるかもしれませんが、
食事や生活習慣によって強化できる部分でもあるし、
間違えると壊してしまうこともあるのです。
大人も氣づいた時から変えていく事が大切ですので
健康維持に、そして健全な精神で活動するためにも
朝食を食べる習慣は重要です。
山本和佳