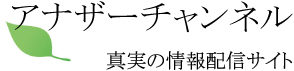玄米の中にフィチン酸という成分があります。
フィチン酸は、ミネラル欠乏症を引き起こす?体内のカルシウムが不足しやすくなりカルシウム不足や骨折がしやすくなる?
そういう風に言われる一方で、強い抗ガン作用がある、農薬や化学物質などを排泄する力がある、肝臓や糖尿病には欠かせない、などなど…フィチン酸について、賛否両論の意見があります。
良くも悪くも云われるフィチン酸ですが、本当のところは一体どうなのでしょうか…。
フィチン酸は、稲などの穀物の種子(玄米)や大豆などの豆類に多く含まれています。
ではなぜ玄米や大豆などの植物に多く存在しているのでしょうか。
フィチン酸が植物に存在している理由は、次世代に「命」を繋ぐための大切な「子ども(種)」を、他の生き物に食べられないよう、守るために植物がそなえた力という説があります。
フィチン酸は米でいうと、外皮の部分に多く含まれています。
白米より玄米のほうがフィチン酸の含有量が多いのはそのためです。
米の糠(ぬか)部分は特に多く、9.5~14.5%がフィチン酸です。
稲のような種子植物は、次世代に命を繋ぐために、フィチン酸がミネラルをキレートする作用を利用し、フィチン酸塩をつくり子孫に栄養として残します。
フィチン酸は、種子にたくさんのミネラルといった栄養素を残そうとする植物の生命維持のために備えた力といえます。
そのため、フィチン酸が多く含まれる糠(ぬか)のある玄米の方が白米よりもミネラルが豊富に存在しています。
フィチン酸のことをミネラルを排出する毒と呼ばれることもありますが、実は、「植物のもつ毒」ではなく、子どもにたくさんの栄養を出来るだけ残してあげようという、子どもを想う親の愛情のようなものなのです。
ただその想いには、子どもに生きるために必要なものを残してあげようとする想いと、外敵から守ろうとする想いの2種類があります。
フィチン酸による恩恵を受ける部分と、そうでない部分(キレートされ消化されにくい状態になる)など、食べる側としてはうまく付き合っていく必要があります。
うまく付き合うために必要なものが、前回お話したフィターゼと呼ばれる酵素です。
例えば、水(ぬるま湯)に玄米をつけることでフィターゼ酵素がつくられます。
昔の人は、一晩釜の中に玄米を浸し、朝炊いて食べていました。
これは、「水につけるとフィチン酸が減り、少し発芽状態になることでフィターゼが生まれて消化がよくなるから一晩水に浸すのよ」と親から教わってきたことではありません。
親や祖父母や親族といった、身近にいる自分より年上の人が行ってきたことを見て、ご飯の支度などを教わりながら自然と習慣になっていき覚えていくものです。
そうした玄米を食べる昔ながらの食習慣の中には「食」を効率よくいただく上で大切な情報が隠されていたのです。
(つづく)
川野 ゆき