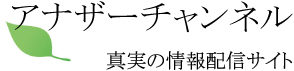玄米の中にフィチン酸という成分があります。
フィチン酸は、ミネラル欠乏症を引き起こす?体内のカルシウムが不足しやすくなりカルシウム不足や骨折がしやすくなる?
そういう風に言われる一方で、
強い抗ガン作用がある、農薬や化学物質などを排泄する力がある、肝臓や糖尿病には欠かせない、などなど…フィチン酸について、賛否両論の意見があります。
良くも悪くも云われるフィチン酸ですが、本当のところは一体どうなのでしょうか…。
今まで4回にわたりフィチン酸についてお知らせしてきました。
今回は、フィチン酸についてまとめたいとおもいます。
フィチン酸は、その独特のキレート作用により、有害なものを体から排出してくれる機能を持ちます。
(特に、有害な化学物質、農薬などに汚染されている食を食べている現代人は、昔に比べ食による病が増えてきたといわれています。)
そのため、フィチン酸を多く含む玄米は解毒作用に優れている食品でもあります。
特に、一度体内に溜まってしまうと排出するのが難しいとされる有毒な金属類もフィチン酸のキレート作用によってがっちりとロックされ、排出できるのは大きな魅力のひとつです。
気になるミネラル吸収率が悪いのではないかといわれている点も、脱リン酵素とも呼ばれるフィターゼにより、フィチン酸の中心核「イノシトール」にくっついている6個のリン酸を全部切り離し(アンキレート作用)フィチン酸が分解されることで、ミネラル分も消化吸収されやすくなります。
また、分解されたIP6(フィチン酸)は、体内にあるイノシトールと化学変化を起こし、IP3が生まれます。
IP3には、抗ガン作用、免疫の強化、循環器系の病気のリスク低下など、多くの効果が発見されています。
玄米に含まれるフィチン酸を効率よく摂取することで、体に溜まった金属排出、豊富なミネラルや栄養素を吸収、そして抗ガン作用、免疫の強化、循環器系の病気のリスク低下といった効果が期待できるのが玄米です。
玄米の潜在能力には目を見張るものがあります。
一昔前まで生活習慣病と呼ばれていた糖尿病などは、典型的な食生活習慣病でした。
今は、肥満、脳梗塞、高脂血症、そしてガンなどの病を抱えている人がたくさんいます。
少しイメージしてみてください。
昔の人は、食べるものも控えめで、肥満の人は少なかったですよね。
ガンは、今みたいに2人に1人がなるとは言われていませんでした。
高脂血症のかたも、血管系を患われている方も、今と昔とでは質が違います。
今は、明らかに食べすぎ、もしくは間違った食生活によって引き起こされる病がほとんどです。
食生活により病気が広がっていくのなら、今の食生活を見直して、昔の日本人が食べていたものは何か思い出してください。
日本人は古来から和食と呼ばれるものを食べてきました。
江戸以前まで、玄米ご飯、そして酵母菌たっぷりのお味噌汁、つけものは、必ずといっていいほど食卓にあったはずです。
さらに、昔はあり、今は廃れつつある大切な食文化があります。
それは、「よく噛んで食べる」ということです。
フィターゼ酵素のほかに、「よく噛んで食べる」ということが、玄米の栄養素を効率よく摂取するには必要なことです。
昔の人は、体感で大切なことを学んでいました。
これまでに紹介してきたとおりですが、玄米は栄養価に大変優れた食材で、完全栄養食とも呼ばれています。
現代人が、本当の意味で玄米という完全栄養食を食べるためには、ただ玄米を食べるというだけでなく、その炊き方や、食べ方がどうだったのかを昔から学び取る必要があります。
どうか、玄米の魅力をのこらず摂取するために、「よく噛んで食べる」「玄米は水に浸しておく」といったことを実践してみてください。
フィチン酸については今回で終了しますが、玄米についての魅力はこれからもお伝えして行きたいと思います。
川野 ゆき