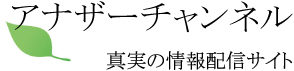どうしてお米は“研ぐ”のでしょうか?
そんな素朴な疑問を解説したいと思います。
白米が日常食としてよく食べられるようになったのは、江戸時代だといわれています。
地方では玄米が食べられていましたが、江戸では白米を食べることが日常だったようです。
その頃の精米技術では、白米にもまだ糠(ぬか)が残っていました。
糠には油分があるためにだんだんと白米は酸化していきます。
初めの内はよくても、長い間米を置いておくと糠臭さが鼻についてしまい、好まれませんでした。
けれど、よく研いで食べることで酸化した糠が落ち、臭いが和らいだため、よく洗って食べられるようになりました。
白米は、糠を落とした精米後でも、若干糠がついています。
今は精米技術が進んだために、昔に比べ糠はほとんどついていないようですが、昔からの名残で今でも白米は水でよく研ぐという風習が残っています。
なぜお米を研ぐのかというと、それは白米の周りに付いた酸化物である糠を取り除く為に行うからでした。
(他にも、汚れや、現代では農薬などを落とすためにも洗われています。)
また、お米は「洗う」ではなく「研ぐ」といいます。
これは、昔は精米しても糠層が多く付着していたので、洗っただけでは取り除くことが出来ず、米と米をこすりあわせて、言葉通り「研ぐ」必要があったからです。
ですので、精米の技術が発達した今では、白米は「洗う」でも美味しく食べられると思います。
逆に、昔のように研ぐと米がつぶれて不味くなるそうです。
さて、これまでは白米についての話ですが、では、玄米はどうなのでしょうか。
実は、玄米は「研ぐ」必要はないといわれています。
白米には、落ちきれない糠がついているために研ぐ必要があるとお話ししましたが、それなら玄米は糠だらけなのにどうして研ぐ必要がないのでしょうか。
ここにも、玄米の良さが隠れています。
例えば、りんごやじゃがいもは、皮がついているままなら日持ちしますが、皮を剥けば時間が経つにつれみるみるうちに色が変わっていきますね。
実は、この皮をむいた状態が白米で、皮付きの状態が玄米なのです。
糠の部分は、酸化を防ぐ皮の役割も担っています。
りんごやじゃがいものように、皮をむいたら酸化して腐ってしまうのと一緒で、お米は、皮である糠(ぬか)を取り除いてしまうと、どんどん酸化していってしまいます。
ポテチと一緒で、袋を開けたら空気にふれてすぐに酸化が始まるので、食べる場合はできるだけ早く食べきる必要があります。
(余ったポテチを洗濯ばさみや輪ゴムで閉じて、また今度食べようというのは危険ですので、止めたほうがいいです。食べきってください。)
白米も、精米した瞬間から酸化が始まりますので、できれば早くに食べきることをお勧めします。
または、酸化した糠の部分を落とすために、古いお米ほどよく「研ぐ」必要があります。
(けれど、よく研げばそのぶん残った栄養素も剥がれ落ちてしまうのでもったいない話です。)
そうした皮を失った白米と異なり、「洗う」だけでも十分においしくいただけるのが玄米です。
でも、よく研ぐように洗うことで、お米が割れて白米が顔を出し、炊き上がると甘味が増すので、あえて研ぐ方もいるようです。
お米の洗い方ひとつを考えても、様々な理由があるのですね。
(つづく)
川野 ゆき